最近、85歳になるおばあさんと接する機会があったのだが、話をしているうちに気づいたことがある。
・時間の感覚、流れ方が独特。現在、過去、の順序が全くのランダム。
・記憶が一日で変わる
・できることとできないことの落差が激しい。
・話が通じていると思うと、全く覚えていなかったり、わかっていないことが判明して、もめごとの原因になる。
・こだわりが強くなる
・感情の起伏も激しくなる
・整理整頓ができなくなる
・集中力があちこち飛ぶので、何をしていたのか分からなくなって、パニックになる。
・探し物ばかりしている。
・・・・と枚挙にいとまがない。そのおばあさんの様子を見て、「え、これはまるでADHDではないか!」と、思った。
普段の生活や学校生活で、配慮を必要とする子供は、「どうして自分だけできないんだろう」「どうしてすぐ忘れちゃうんだろう」と、彼ら自身、非常に困っていて、理解されないがゆえにいじめにあったり、教師からも不適切な扱いをされたりしている。
自分の特性を理解して、できることとできないことをはっきり自覚することは重要だと、思う。
そして、このおばあさんも「周りの人ができるのに、自分できないって情けないんだよね。毎朝起きて、今日はどこにいるんだろう、何月何日?とあせってしまって、わからなくなっていくのが恐ろしい。耳も遠くなっちゃって、だれが何を話しているのか、まったくわからないとさびしいやらなさけないやら、すごく孤独に感じてしまう」と悲しそうに言う。
ああそうだ、配慮が必要な子も、必死になっていまわりの子についていこうとするけど、できなくて切ない淋しい思いをすることが多い。
そして、お年寄りも、自分の体の機能があちこち衰えていき、思うように動けなくなり、考える気力もなくなっていく自分に孤独を感じる。
「どうして自分はできないのか」「どうやったら、話が通じるか」「どうやったら、自分のつらさを理解してもらえるか」
きっと、「普通の人」の何倍も、そういうことで悩んでいるのだろう。
どうせわからないから、とか、どうせ耳が聞こえないから、といって、はなから仲間外れにするのではなく
耳が聞こえなくても、文字で書いたらわかるかもしれない。違う説明をすれば、わかってもらえるかもしれない。
そういったことを頭に入れて、接するようにすればいいのではないだろうか。

-400x400.jpg)

-400x400.jpg)
-400x400.jpg)



-400x400.jpg)


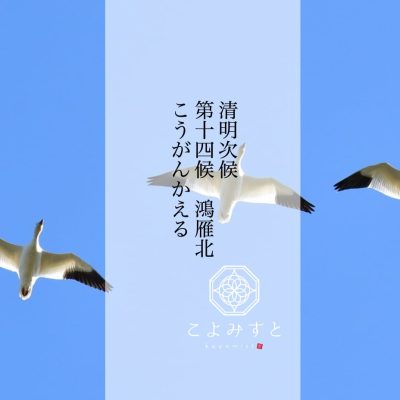
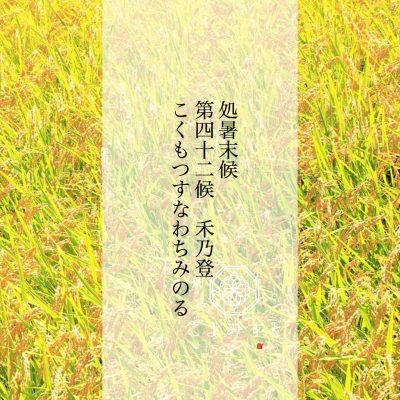

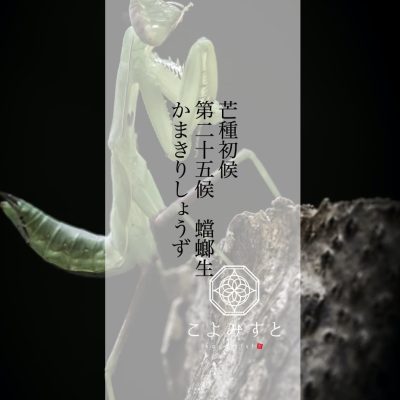

-400x400.jpg)

-400x400.jpg)
-400x400.jpg)
この記事へのコメントはありません。